一発ネタのはずだったパラレルSS 1
「ジェクト様ー! おもいっきり投げてみてー!!」
「なにー! 俺様の最速のボールがみてぇってか! 特別だぞ!!」
何の変哲も無い公園。地元の少年達が3on3を楽しむ程度の簡素な屋外バスケットコートに、突然地元チームの大エースが飛び入りで現れた。
休暇に暇をあかして出てきたというエースは、あっというまにバスケ少年やら、その盛り上がりを見たよくわかっていない女子大生やらにとりかこまれ、上記の声援を掛けられた。元々フリーダムもいい所の性格をしている彼は、普通バスケットボールでは絶対にやらないであろう、コンクリートの壁に向かって全力投球というその無茶な要求に快く答えたのだ。
「おめーら目ェかっぽじってよく見てろよ!…3、2、1 おりゃあ!!」
豪速球は真っ直ぐ壁にぶつかって、地面に跳ねる事も無く俺様の元に戻り大喝采! …と、いうのが彼の計画だったのだが、そこはただの公園。安普請なコンクリートの壁。
なにか埋まっていたか、作りそのものが平らではなかったか、ちょうどそこにでっぱりがあったらしい。勢い良く壁にぶつかったボールは珍妙な方に向きを変え、勢いはジェクトの想定そのままに、方向だけはあらぬ向きへ飛び去って行った。軌道の先で壁のようになっていたギャラリーがクモの子のように散らばる。最悪な事にその向こうにいたのは、ベンチで父親の膝の上に乗り、日傘をさされている…女の子。
「げ!あぶねぇ!!」
言うも、遅い。日傘が飛んだ。
やっちまった!さすがに青くなったジェクトがそちらへ駆ける。ころころと日傘が転がったその元の場所では…父親、というには些か若い銀髪の青年が、何事も無かったようにそのボールを受け止めていた。銀の髪をかかえて伏せた少女の頭上で。
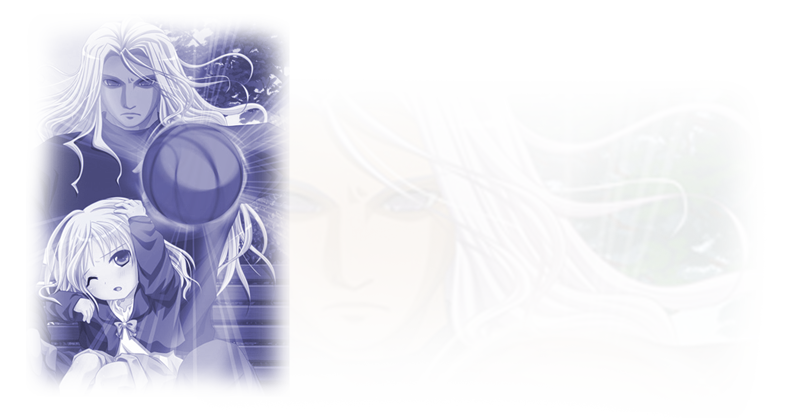
やや予想外の事態に、安堵しながらも呆然とし、ジェクトは駆け寄る。
「すまねぇ、手、大丈夫か?」
「……が。」
「あン?」
「目をかっぽじっては、見えんと思うがな。」
軽く波打った銀髪に薄紫の瞳、褐色の肌とえらく秀麗な顔立ちをしたその青年は、さらりとそう言い、ボールをジェクトに投げ渡した。
数日後。日曜日の午前中に鳴ったチャイムに、1階で留守番をしていたセシルはいつもの様に玄関へかけていった。午後から友達が来る予定だったけど、早くきたのかな、などと考えながら。
「はーい。」
「よ!」
がちゃりと開けると、そこにいたのはセシルの知らない顔だった。いや、正確には知っている。凄く知っている。だけど。
「お、こないだの嬢ちゃんだな。あんときゃびっくりさせて悪かったな。」
そう言って突然わしわしと、撫でられた。ごつごつとした大きな手で。あまりの事に声が出なかった。ニカっと笑ったその顔を見てセシルは…
「…っにーちゃん! にーちゃあぁん!!」
脱兎のごとく2階へ駆けて行った。
「で、そなたが如何して此所に。」
居間でどっかと胡座をかき、出された麦茶を一気に客人…ザナルカンドエイブスのエースは煽った。先ほど彼…ジェクトを出迎えた少女のような少年(女の子ではなかったらしい)は、ジェクトの向かいに座るあの銀髪の兄(やっぱり父親じゃなかったらしい)の後ろに隠れるようにして様子を伺っている。
「あー、まあ話すと長ぇんだけどよ。」
「構わん。」
「監督にポロッとしゃべっちまってよ。詫びてこいって言われちまった。で、此所にいる。」
何も長くなかった。ほれ、と無造作に菓子折りの入っているであろう手提げの紙袋を差し出した。何が入っているかわからないがどう見ても、扱いが悪い。ケーキならすでに戦闘不能になっているだろう。兄はそれを黙って受け取った。
「…随分と端折ったようだが。」
「あ?何がだ?」
「如何して此所が判った。」
問題はそこだろうと言わんばかりの目でエース選手をねめつける。が、ジェクトもさるもの、全く気にする様子はない。
「ああ、あの公園の連中に聞いたんだよ。おめー結構有名人だったぜ。向かいの大学の天才だってな。」
僅かな間。
「…それで?」
「それでって?」
「それだけでは判るまい。」
「ああ。俺あそこのスポーツ特待生だったからよ。先公から聞き出した。で、ここに来た。これで全部だよ。満足したか。」
「宜しい。そこまで話して初めて事情説明だ。覚えておけ。」
「…てめぇ……。」
エースをエースと完全に思っていない態度である。結局ジェクトがあしらわれる形になった。
「にいちゃん、せっかく来てくれたのにあんまりジェクトさんいじめたら、可哀想だよ…」
背中に半分隠れたままの弟が、おそるおそる兄に意見した。
「お、坊主俺の味方してくれるのか!いいガキだな!」
頭を撫でようとして手を伸ばしたら…完全に隠れられてしまった。
「……俺、まだ怖がられてる?」
自業自得とはいえさすがにこれは、エースとしてヘコむ。が、兄貴のほうから意外な言葉が出てきた。
「そうではない。この子もそなたの試合は欠かさず見ているからな。人見知りをする子だ、単に緊張しているだけだ。」
「お! なんだよ坊主俺のファンだったのか!」
兄の背に隠れたまま、弟はこくりと頷いた。
「そーかそーか! じゃあびっくりさせちまったワビに、俺様がとびっきりのサインをしてやろう。なんかもってこいよ。」
「ほんと! にいちゃん、ボールもってきていい?」
「ああ。構わん。」
弟は嬉しそうな顔をしてぱたぱたと玄関に駆けて行った。そして小さな身体に抱えてきたのは、確かにエイブスの公式ロゴマークが入った子供用のバスケットボール。おずおずと、ジェクトに手渡した。ジェクトは自前のサインペンを取り出し、手慣れた様子でそれにさらさらと書き込んでゆく。
「…筆記用具だけは持ち歩いているのだな。」
「エースの身だしなみ、ってやつよ。」
「それで、そこまでリサーチ済みということは、名前も判っているのだろうな。」
「おうよ、先公に聞いてきたぜ。えーっとセ… せ、セ……」
兄を指差したまま、ジェクトは固まった。
「………忘れた!」
「威張るな馬鹿者。」
ピンポーン。
「はーい。」
再び家のチャイムが鳴った。両手で書かれたばかりのサイン入りボールを抱きしめたセシルが玄関へ走る。どうやらこの家、接客は弟担当らしい。
「…まあ、そなたの心意気は受け取った。怪我もない。そう気に病む必要性はない。」
「そうみてーだな。とりあえずすっきりしたし、そろそろおいとまするぜ…」
「うわーーー!!マジでジェクトだーーー!!!」
立ち上がりかけたエースをそこで引き止めたのは弟…セシルの一つ年上の友人、カインだった。
昼もすっかり過ぎていた。
結局夕方まで雪崩れ込み、買い物から戻った母と仕事から戻った父が、素性はよく知らないまでも「せっかくセオドールのお友達が来たのだから」と、ほぼ初対面だと言い張る兄の意見を全くの空気扱いにする形で、夕飯までご馳走するに至っていた。帰宅を渋るカインはなんとか宥めて帰した。
「今度、次の試合のチケット送ってやっからよ。さっきの友達と見に来いよ。」
「ほんとー!」
「おうよ、男に二言はねぇぜ。」
セシルは完全に懐いていた。そしてそれに比例する様に、セオドールの機嫌は悪化していた。
「それは判った。だが余りふらついているようなら、そもそもその試合に出れなくなるのではないか。いい加減帰れ。」
すでに暗にですらなく、明確に帰れコール。横で母親が声を殺し笑っているが、構っている場合ではない。とにかく、弟が他人に懐くのが腹立たしくて仕様がないのだ。しかも、自宅で。だた当のジェクトは全く気がつく様子もなく飄々と答えた。
「ああ、今日はオフだから呑もうが何しようがかまわねーよ! ああ、でもあんま遅くなると嫁に怒られっかな?」
「…嫁?」
あまりに予想外の単語がジェクトの口から飛び出して、ぴたりとセオドールの箸が止まった。
「おう知らねぇ? 別にかくしちゃいねーんだけどな。ウチには世界一いい女と6つになる世界一可愛い息子様がいらっしゃる訳だ。 まあ、俺様も人気者だからなかなか 構ってやれねーんだが…」
「今直ぐ帰れこの馬鹿者が!!!!」
力一杯語尾を被せてちゃぶ台返しの如く怒鳴った長男が、その豹変に度肝を抜かれたジェクトをひったてて車に押し込む迄にかかった時間は、ものの30秒にすら満たなかったという。
「僕よりちっちゃい男の子だったよ!」
幾年か振りに大声を上げた兄に一瞬時が止まったものの、「僕もいくよー!」と助手席(専用席)に乗り込み同行したセシルが、身振り手振りで母親にその時の様子を話す。車内からかけた電話を受け、高級マンションの玄関で待っていたエース改め只の酔っぱらいの妻は息子を連れ、兄となかなか壮絶な謝罪合戦を繰り広げたらしい。当のジェクトはやはり飄々としていたそうだ。
「…全く、あの年頃の子を置いて他人の家で夕飯などもっての他だ。信じられん。」
ソファーに沈む長男はまだご立腹だ。
「あはは…にーちゃんは必ず帰ってきたもんね。」
まだ機嫌の悪い兄が心配なのか、セシルがとてとてと側に寄って膝の上に座る。大体、原因がなんであろうとこれで兄の機嫌は上向く事を弟は心得ているのだ。
「うむ。同列に並べるつもりもないが、可能な限り共に時間を過ごすというのが家族の勤めではないのか。」
案の定、兄は少し落ち着いた口調でセシルの頭を撫でた。
「やあ、なかなか耳に痛い言葉だなそれは。」
そう言って苦笑いするのは向かいに座る、技術者である父。
「ああいえ、仕事だとか試合だとか、そういう物は別ですが…。」
どちらかというと穏やかな性格をしている父と弟に包囲されては、さすがに気を落ち着けるより他ない。セオドールが一息ついたのを見計らったようにセシリアが茶を持ってきた。
「あまり責めるものでもないわよセオドール。才能のある人というのは人と対等の付き合いをする機会というものがどうしても少なくなるもの。きっと久しぶりだったのじゃないかしら。貴方だってよく解るでしょう?」
にこりと柔らかな微笑みで諭されれば長男は黙るより他ない。彼も幼い頃からの天才肌なのだ。そういう状況は痛い程よく解る。
止めを刺すように、母親は言った。
「いいお友達が出来たわね、セオドール。よかったじゃない。」
一瞬、ぽかんと口を開けてしまった。
「…ですから、今日で高々2度目だと……」
「充分じゃない。それに、あんな風に感情を出すあなたなんて、久しぶりに見たわよ。」
にこにこと、しかしどこか強気に笑う母には抵抗出来ず、助けを求める様に周囲を見回した。が、父も弟も似たような反応で、どうやら完全に孤立無援になったらしい状況にセオドールはひとつ溜息を吐いた。
言われてみれば、家族も含めあれだけ人に言いたい事を言ったのも何時振りだろうかと思う。無理をしていたつもりもないが、無意識に「求められる自分の姿」を作っていた所はあるのかもしれない。確かに、妙に解放されたような気分になっている自分がそこにいた。
と、セシルが何か思い出した様に手を叩いた。
「あ、そうだにいちゃん。ジェクトさんからお手紙預かったよ。」
「…手紙?」
また似合わない単語がでてきた。手渡されたそれは手紙というよりメモ、字に至ってはかの男の性格をを体現したかのような、好意的に見れば走り書き。普通に考えるなら、落書き。一瞬では判別出来ないその形状はメールアドレスらしき書式と、以下のような意味を表記しているようだった。
『俺様のメアド。あとでメールよこせ。飯サンキュー。そのうち借りは返すぜ。』
「…この上なくあの男らしいな。」
まあ、思い返せばそう悪い時間でもなかったかとひとまずメモを胸ポケットに入れ、セオドールは膝の上でにこりと笑うセシルを抱え直した。
パラレルといえばDFF学園モノですが、逆にカオス側が学生年齢のパラレル物って見たことがないなあと思い、ちょっとやってみた。兄スキーとしては通ってもいい道かなと…。カオス側っていうか、単に兄さんがフツーの人生送ってたらっていう、月一家+αパラレルだけども。ジェクトさん以外のカオスサイドをどうやって出したらいいかまったく想像がつきません!
ああ、皇帝は成績的にライバルになれそうだが、学生のマティウスとか想像するのつれぇwwww
まあ、細かい設定は貴方の脳内にってことで。