やってしまったルビカンテSS 8
軽い頭痛と共に声が聞こえる。
憎め、憎めと。
僕はもう随分と前からその誘惑にお断りを入れている。
昔はその声に流され、本当に全てを憎んでしまおうと思ったこともあった。そうすれば楽になれるのは分かっていたから。
だけど、ルーベルが来てから変わった。
人は憎いばかりものではない。分かりきっていたそれをルーベルの存在は再確認させてくれる。
「そばにいる」。その言葉を愚直なまでに守り続ける彼に、僕の心はどれだけ救われただろう。
ルーベルはもう、ミシディアに戻っても他の追随を許さない腕の魔導士になった。
だから、もう僕の横にいる価値はない。
あんな口約束、律儀に守る必要はない。
…その一言を、僕はずっと言えずにいる。
憎め。人など、信じるな。
その言葉に今日も僕は、丁重にお断りを入れた。
満月が近かった。
今日も近くまで来れば、キリエは気配を察し嬉しそうに家から飛び出してきてセオドールに抱きつく。彼もまた、嬉しそうにキリエの小さな身体を抱え上げ、頭を撫でるのだ。
あれから二月ばかり、私とセオドールは週に2、3度はこの家に通うようになった。近所というにはあまりに遠いが、体力をつける訓練にもちょうど具合がよかった。
老人と子供の二人暮らしはやはり侭ならぬ事が多いのだろう。屋内は私が最初にセオドールの家に入ったあのときよりも荒れており、早急な修復が必要な箇所がいくつもあった。まず我々は家屋の修繕からとりかかった。
「情けは人の為ならず、っていうか…人の行為って回りまわるものだな。」屋根の上でしみじみとそういったセオドールが忘れられない。かつて私がこうして家の 修理をしたことを覚えていたのだろう。些細ではあるが嬉しかった。
キリエは未だ言葉らしき言葉を話すことは出来なかった。「言語中枢が完全に駄目になっているのだろう」。セオドールはそう言った。曰く、彼に言葉は通じ ず、それはただの音、良くて合図としてしか捉える事しか出来ないのだそうだ。だからキリエは五感と気配、身振り手振り、言葉以外の方法で世界を認識しているのだと説明した。人は言葉で世界を認識する。だから言語が死ねば人としての知力は大幅に落ちる。真っ当な方法でコミュニケーションが図れない彼には、この環境が一番良いと思う…そう、翁のいないところでセオドールは付け足した。
ふた月もすれば家屋の修繕もほぼ終わり、資材の買い足しも一先ず必要なくなった。今日は午前中から遊び通しだったキリエは、疲れたか昼食を食べて眠ってしまった。そういう訳で珍しく、居間には私とセオドール、翁の三人がいる。
そろそろ心を開いても…と、思うのだが、相変わらず翁の事は苦手なようで、私達の話に入る事もなく部屋のあちこちを見て回っていた。
「あれ。」
不意にセオドールが声を上げた。何かと思い振り返ると、少し高い位置に備え付けられた棚から、一冊の本を取り出していた。
「…魔導書?」
「こ、こらセオドール! 人様の家でいくらなんでもそれは失礼だ!!」
流石に焦った。明らかに翁の身長からは高すぎるその位置は、セオドールや私の目線よりも少し上。文化によっては神棚とも取れるような高さの場所に置いてあったのだ。大事な物である事に間違いはなかろう。
「ああ、ごめん。済まない。」
淡々と謝罪してそれを元の位置に戻そうとしたセオドールに、翁が声をかけた。
「構わんよ。興味があるなら見ても良い。」
「よ、よろしいのですか翁。」
驚いて聞き返した私に、翁は微笑んで答えた。
「儂にはもう無用の長物じゃ。キリエにも…必要なかろう。色々良くして頂いた礼じゃ。よければ、持って行け。」
セオドールは本…特に魔導書類には目がない。そこに記されたものが知った知識であろうがなかろうが、新しい本が手に入れば その日の予定を全て忘れて没頭する程だ。正直、ありがたい礼だった。
「…かたじけない。」
「よい。大事にしてやってくれ。」
「セオドール、礼を…」
そう言って振り返れば、すでに彼は立ったまま魔導書の世界に入り込んでいた。
「…申し訳ない。」
「よいよい。書き手も、喜ぶであろう。」
翁は柔らかく笑って言ってくれた。出会った当初のあの刺々しさから見れば、なんと角が取れたことか。私も微笑みを返した。
今思えば、どうしてあの時彼のことをしっかりと見ておかなかったのだろうとそう思う。多分きっと…その手は震えていたのだ。
結局、帰る時間までキリエは目を覚まさなかった。セオドールが「またな」と眠る彼に一言だけ声をかけ、私達は家路についた。いつものように月が昇り始める時間。今宵は満月のようだった。こんな時間に出歩く事も全く珍しくなくなったが、そういえば以前は随分と満月の夜を怖がっていた。最近はそんなこともすっかりなくなったな…と、そんな事をふと思った。家に辿り着くまでセオドールは静かだった。おそらく、魔導書を思い返し考え事をしているのだろうと、私はさして気にも留めなかった。
家に着き、私が就寝の準備をしていると、ぽつりとセオドールが言った。
「あの魔導書な。」
「ああ、翁から頂いたものか。駄目だぞ、今度会ったときはきちんと礼を言わねば。」
「ん?ああ、そうだな…。」
勢いを削がれたようなセオドールの声。そのまま、暫しの間が空いた。
「…すまない、話の腰を折ってしまっただろうか。」
「少しな。」
「…申し訳ない。」
空気を完全に読み間違った。バツが悪い事この上ないが、続きを、と先を促す。軽く苦笑いをして、セオドールは話し始めた。
「あの魔導書…。僕に家にあった物とほぼ同じだ。」
「! 本当ですか!!」
「…ああ。間違いない。」
「では、貴方が学んだというその魔法の…!」
「そうだ。」
心の底から驚いた。そして、思わぬ出会いに興奮した。それは私には絶対に見ることが適わないと思われていた、あの彼の師たる聖典とも呼べるそれではないのか! 前後を完全に見失うほどに私は高揚していた。
「セオドール! ぜ、ぜひそれは私にも…!!」
鷲掴むようにしてセオドールの肩をつかみ、ゆすった。突然の反応に驚いたのか、彼は唖然とし口をあけた。
「お、おいおいルーベル、落ち着け!」
「…は!も、申し訳ない!」
困ったような彼の声にあわてて両手を離す。肩口にはくっきりと私の手の跡がついてしまっていた。重ねて謝罪をしようとすると、突然セオドールは快活に笑った。
「そうだな、うん。今更考えても詮のない事だな。」
「は…何か?」
「いや、何でも。…読むか?」
「是非!」
何かをはぐらかされた気はしたが、正直私の心はそれどころではなかった。手渡されたそれを恐る恐る開き、見つめる。びっしりと書かれ文字は、確かにセオドールの教えと同じ意味を示す言葉に相違なかった。
「先に休んでいるから。夜更かしも程ほどにな。」
笑いながらそう言って寝室に入った彼に、どんな言葉を返したのか正直覚えていない。
それから先の記憶も…
別の意味で、曖昧になってしまった。
確かに、父さんの字だった。
幾つも同じ内容の本を書いたから覚えてしまったよ。そう言って笑っていたから間違いないだろう。
何故あそこに。
答えの種類は幾つもなかった。
僕はずっと、あの老人の顔をまともに見ていない。
…見られなかった。何故か。
理由は。
見たことがあるからだ。どこかで。
その場所は、幾つもない。
導き出される答えは、考えたくなかった。
やっと、穏やかな生活になってきたのに。
何よりも。
あの老人は、キリエの肉親なのだ。たった一人の。
だから。
心がざわめいて、僕は目を覚ました。
起き上がり、ルーベルが来てから据え付けられたカーテンを開ける。満月が2つ浮かんでいた。
嫌だ。満月の日は力が疼く。あの声が強く聞こえる。僕は目をそらした。昔はそれに躍らされるように一人暴れる事もあった。苦しくて、悲しくて憎くて、そうせずにはいられなかった。今はそこまで自分を見失うこともなくなった。それもあいつのおかげだ。ずっとこのまま…なんてことはない。それは分かっている。 だけど、可能な限り長い間、このまま…
ベッドに戻ろうと振り返り、目を上げて僕は息を呑んだ。
そこに、あの「声」が居た。
月光に照らし出されるように現れたそれ。青く長いローブ、それに負けぬ程青白い肌、禿頭。光のない目、それなのに、明確に分かる表情で男は…ニヤリと笑った。
「…漸く、ここまでの力を蓄えた。」
間違いなく、あの声だった。僕は…動けなかった。「声」は、ねめつけるように僕を見た。
「……如何したゴルベーザ…。随分と、温くなったではないか。」
「…うるさい。僕はそんな名じゃない…!」
必至に言い返す。情けない事に自分の声は震えていた。「声」は続けた。
「今更何を言う。お前は「捨てた」ではないか。お前の庇護すべき者を。自らのその手で。忘れたのか?」
ひっ… 自分が息を呑む声が耳につく。頭から足先まで電流が突き抜ける感覚。忘れない。忘れる訳ない。僕は…僕はこの手であの小さな温もりを… 母さんの残したそれを
「やめろ!!!」
「く…はははは。逃げるか。目を逸らすか己の罪から。憎しみから。ならば思い出させてやろう。教えてやろう真実を。そして思い出せ。人とは…憎むべき存在であるという事をな…。そしてお前は、私の……」
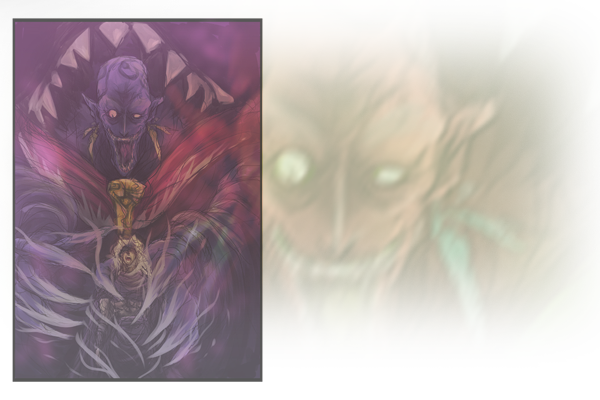
そして「声」は…消えた。
静寂。圧倒的な。
虫の声も、草木が風に揺れる音すらも聞こえない。
あの夜と同じだった。
「…キリエ…!」
僕は、走り出した。
はっと、私は意識を取り戻した。
刻まれた文字から目を放し、顔を上げる。明かり取りのためにカーテンを開け放していた窓を見た。2つの満月はそれだけで蝋燭など必要がない程に、明るく闇夜を照らしていた。
眠っていたのだろうか。その割に、脳ははっきりと覚醒している。まるでストップの魔法から解放された時のようだった。
「…え?」
自分の思考にひととき止まった。振り返り部屋を見る。意識を集中すると、僅かに魔力の残滓を感じた。背中を嫌な汗が流れた。
早足でセオドールの部屋に向かう。扉に手をかける。
「セオドール!!」
開け放ったそこに彼の姿はなかった。開けられた窓、風にそよぐカーテン。2つの月が、不気味な程煌々と輝いていた。
深夜、物音を聞いてキリエは起き上がった。昼間にいいだけ寝てしまったので目が覚めていたのだ。こんな夜中に誰だろう、とかセオドールが忘れ物をして戻ってきたのだろうか、とかそんな風に言葉で思考する能力をキリエは持っていない。だが、この家に訊ねてくる人間は自分と祖父以外、セオドールとルーベルしかいないということは彼は認識していた。だから、表に出た。何の疑いもなく。
そこにいたのは…見た事のある顔だった。
セオドールと会った時。あの日里で見た、怖い人達。
怖い人達が、こちらを見ていた。その手が、伸びてきた。
逃げろ、キリエの本能が伝える。それに従う前に、彼は襟首を掴まれていた。ぶちり。と何かを引き千切られる。
「…間違いねえ。あいつの『お守り』だ。」
一人の男がそう言った言葉を、キリエは認識出来ない。
がたがたと表の騒がしさに老人は目を覚ました。最近魔物の動きが少し活発化している。ここまで来たのかと起き上がり、枕元のロッドを手にした。キリエに声をかけるかと隣のベッドを見ると、そこに孫の姿はなかった。
「…キリエ!?」
青ざめた老人が立ち上がった瞬間、激しい音を立てて扉が開かれた。
夜の森を私は走っていた。かつてより体力がついてゆとりの出来た身体は、足と同時に頭も急速に回転させていた。
キリエと老人の住む山小屋は町を挟んで反対。生半可な距離ではない。普通に考えれば懸命な彼が今の時間から向かうはずなどなかった。だが私の本能は告げて いた。間違いなく、あそこだと。しかし、もし本当にセオドールがあの小屋へ向かったとして、はたして走るなどというそんな時間のかかる手段を使うだろう か。私は足を止めた。
「…テレポか?」
曰く、あの術は本来『脳裏に焼き付いた場所に転移する』術なのだそうだ。だが、通常人は目に入ったものの全てを正確に記憶している訳でも、全てを深く細部 まで覚えている訳でもない。適度に情報を整理し略し、効率よく覚えているのだそうだ。だから、ダンジョンなど異界に入る入口…というような、意図して覚えようとしたり、注意深く観察する場所に対してのみ、結果あの魔法は良く効果を発揮する。そういう理屈なのだという。だから、本当はよく覚えている場所なら、多少の誤差はあれど一瞬で移動することは可能なのだと、そうも言っていた。失敗すればどこにどう飛ぶか身の保証はないけれど、とも。
あの小屋まで転移する自信は正直なかった。だが。
「…村までなら。」
ここ数年、定期的に通っていたあの場所なら、相当覚えている。物珍しいものを見るたびに、これは何かとセオドールは訊ねてきた。だから、細部までよく。
「…やるしかない。」
口に出せばそれは誓いとなり迷いは無くなる。私は意識を集中する。より、印象深く覚えているその場所を探す。
「テレポ!」
成せば成る、という言葉を初めて私は体験として実感した。
「久しぶりだな、ルクソルの親父さん。」
そこにいたのは、老人には忘れようにも忘れられない顔――。あの日、あの時、人生最大の過ちを犯したとき共に居た男のうちの…3人。
「お…お前達……」
「随分と年喰ったみてえだが、意外と近くにいたんだな。灯台下暗しとはよく言ったもんだぜ。」
「ど、どうしてここが…!」
老人の声は震えていた。対する男は、笑っている。
「声が聞こえたんだよ。親父さんも知ってるだろ、あの天の声。」
「な…!あ、あれは天の声などではない!悪魔の囁きだ!!」
絶叫した。己の過ちに。
「どっちでもいいんだよ。僕たちはもう戻れない所まで来たんだ。さあ。…あの本を渡してもらおうか。クルーヤの…禁書を!!」
男の言葉に老人は歯噛みした。息子を殺した憎い敵を前に。そのうえまだあの書を狙っていたとは、正直思わなかった。
だが、次の瞬間老人は口角を緩めた。
「…もう、ないわい。」
「なに?」
「人にやってしもうた。こんな儂らに良くしてくれる若者がおってな。あの本は儂らのような邪念に溺れる者が持つべきではない。持つべき人間に手に渡したわ!!」
そう言って高笑いした。師の残した遺品。それはミシディアに魔法が伝わる前に書かれたという、魔法の本質を記した魔導書。
自分達には到底理解できないような深い物理現象。科学知識。それに根ざした魔道の理。うわべだけを読み、知った被って徒に振るえば、理を知らぬそれはコントロールを失い暴走した狂気の魔法となった。だから、ミシディアは今それを禁書とし。現在は系統立った制御の容易な魔法のみを伝授するようにしている。師も、それに賛同したのだ。そして、幾つかあったその魔法の「原書」ともいえるそれを、僅かな数を残し全て焼き払った。あれは…そんな原書の一つだったのだ。
「…そいつは何処にいる。」
苛立ったようにかつての同胞は言った。
「知らん。」
老人は冷酷に返した。
「…そうかい。じゃ、もう用はねえな。アンタも死にな。」
後に控えていた男が何かを投げつけた。どさり、と老人の前に落ちた。動物か? 最初に思ったのはそれだった。それは月光に照らされて輪郭を現した。
「――――キリエ――!!!!」
「はははは!そんな判りやすい目印ぶらさげて歩くからだ!! 最も、最近は妙な護衛がついてて手が出せなかったんだがな! こんな時間じゃそうもいくまい。天の声様々だぜ!!」
高笑いする男を老人は、現実を認識出来ないまま呆然と見上げる。黒い、邪悪な気が男達にまとわりついていた。それはあの日、自分も包まれたその邪悪な意志そのものだったのだが、今の老人にそれを理解する事は出来なかった。ロッドを持つ右手に魔力が凝縮される。
老人の絶叫と共にそこから激しい雷が吐き出された。男は笑いながら、黒い炎を持って迎え撃った。
ざくり、と足が草を踏む。まだそこまで慣れない場所への瞬間移動はかなり手間取ったが、徒歩で来るよりは遥かに早くそこへ辿り着いた。息を吐き、僕はキリエの山小屋を見上げた。
黒い、気配。
あの声の。
ざわりとした嫌な予感が背中を走り抜けた。
声もかけず許可も取らず、僕はドアを蹴破った。
そこにあったのは、無造作に転がったあまりに無惨なキリエの姿だった。
虚ろに見開かれた目には驚愕と絶望が。衣服は裂かれ、アザと傷に塗れた身体には、鼻につく白い液体。無造作に転がされた彼の足の付け根には、余りにも酷い裂傷が走っていた。そこに命の鼓動はない。見て明かだった。
怒り、などという感情はとうに通り越したらしい。
恐らくは冷たいとも取れるだろう目線で僕はそれを見ていた。首をあげ、目の前の人間らしきものを確認した。
見覚えの有る3人。その足下には年老いた老人が転がっている。そちらの息はあるようだった。気が高ぶっているのであろうその人間共は、なにかを言ってこちらに剣を…杖を次々に振り上げてきた。そこにあるのは黒い気配。明らかにあの声の、あの気配。
だがそんな事、今の僕には関係なかった。
ころして おけば よかった
その思いだけが、何度も何度も、僕の胸を去来していった。
「う…」
老人が唸りをあげた。肉が裂け、焦げる音に意識を取り戻したのかも知れない。ゆっくりと仰向けになり、こちらを見た。
「……セオドール…?」
目は見えているのか。そんな事を思った。
「…本」
「……?」
「ありがとう。それだけは伝えておく。懐かしいものを見させてもらった。」
「…。」
戸惑っているようだった。それはそうだろう、今老人の身におきた事柄からは余りに遠い話題だ。だが、それもどうでもよかった。
「一つ聞きたい事がある。」
「な…にを…?」
「何故貴様が父の本を持っている。」
瀕死の重傷を負った老人とは思えぬ絶叫が、山々に谺した。
町から先は走った。ただ走った。時間は大幅に短縮されたが、それでも随分かかってしまった。セオドールは無事なのか、無事で居てくれ。それだけを祈り続け走った。山深く分け入った時、叫び声が聞こえた。翁の声だった。
やはり何かがあったのだ。私は全力で走る。だが、焦れば焦るだけ足下を取られ掬われ、却って遅くなるような感覚に私は焦れた。山小屋は、もうすぐだというのに―――!!
「何処かで見たと思っていたがな。あの水晶…。里に居た、父さんの弟子…ルクソル・エルスが身に着けていたものだな。父が魔法を皆伝したものに「好きに使え」 と素材を渡していた、あれだ。貴様はその父親だったのだな。随分と変貌していて、直ぐには判らなかったぞ。エレソンは…変名か。確かあの男は父さんの意見に懐疑的だった。」
「ゆるして…ゆるしてくれ……!わたしは、わたしはあの声に声にいいいいい!!」
「声?」
訊ねても、老人は只ひいひいと声にならない声を上げ、後ずさるだけだった。
この老人にも声が聞こえていたのか。だが、それもどうでも良い。
「そうか。ならば貴様も……父を殺したのか。」
淡々と、私はそう言った。
「うあああああ!!!!」
びしり。己の身体から魔力が爆ぜた。見上げるとそこに黒竜がいた。
「助けて、たすけてください…!」
命乞いをする老人を、私は静かに見る。
「…そうだな。必要以上に貴様等を恨む気もなかった。だが」
振り返る。そこに有るのは、私が外套を被せた幼い…遺体。
「キリエは死んだ。貴様を生かしておく理由は…無いな。」
天を揺るがす絶叫は、途中で冷気に掻き消えた。
私が辿り着いた時、すでに山小屋は巨大な炎に包まれていた。
「そんな…!」
何故、どうしてこんな事が起きるのか私には理解出来なかった。
炎の前に人影が揺れた。
爆ぜる炎に揺れ、輝く銀糸。肩を越す程伸びたそれは上昇気流に乗って美しく舞い上がる。外套は失われ、年を思わせぬ確りと出来あがった体躯が衣服の上から でも容易に見て取れる。長身をゆっくりと翻し、すっかり幼さの抜けた「秀麗」と称するが相応しい美しい顔立ちが、赤い炎を照り返しながらこちらを見た。
…黒い竜を纏ったその冷徹な薄紫の瞳は、かつて一度だけ見たあの、セオドールの目だった。
「ルーベルか。」
「…セオドール…」
情けない事に足が竦んでいる。いつかの狂乱を思い出した。しかし予想に反して、セオドールはとても静かに口を開いた。
「…早く、此所を去ると良い。」
「…? 何を…」
「私はもう人では無い者になる。だから、お前は去れ。」
「…何を言っているセオドール! 何があったんだ!!」
振り絞り、叫ぶ。セオドールは、視線を月へと向けた。
「…あの声に、従う事にしたよ。」
「声…? 声とは君が幼い頃に言っていた…? あれは、もう聞こえないのではなかったのか!?」
セオドールは僅かに、笑った。
「聞こえていた。聞こえていたさ。お前が来てから構わぬ手立てを覚えただけでな。向こうもあれこれ手は打ってきていたが、それでも無視する事が出来ていた。それだけだ。」
「そんな…!」
それは…あの「声」とは、心の声などではなかったという事か? そしてそれは今の今まで続いていたと言う事なのか。それでは…私はこの数年、彼の側で、彼の何を見ていたというのだ! まるで無能ではないか!!
セオドールはこちらを見て…にこり、と笑った。出会った頃のあの微笑みだった。
「…漸くわかったんだよ。僕はもうあの声からは逃げられない。弟を捨てたあの時から、もう僕の手は罪と闇に染まりきってしまってたんだって。それに、やっぱり…やっぱりね」
俯き…そして顔を上げた。
「私は人が、憎い。」
「嘘だ!!!」
私は叫んでいた。
「貴方は人を憎んでなどいない! ただ、傷ついていただけだ! 当たり前の愛に飢えていただけだ!! その証拠に貴方はあれほどキリエを愛したではないか! そうだ…キリエは、キリエはどうなさったんですか!!」
「キリエは殺された。」
「な…!」
「祖父は私が殺した。」
なにも。何も言えなかった。
「キリエは人に成り損なった人間だ。キリエを殺したのは人間だ。そして私も…人の理を外れた人間だ。」
黒竜が、労るように彼の頬に身を寄せる。私は…ただ震えていた。
「私のこの身には、人成らぬ異系の血が混じっているのだよ。」
関係ない。その一言が言えなかった。ならばこれほどの力と美しさも合点がいくと、そう思ってしまった。
「…それでも、僕が今まで人でいられたのはお前のおかげだよ、ルーベル。感謝してる。」
「…セオドー…ル…?」
「うん。その名で呼んでくれたから。だから今までそれを、忘れないでいられた。…けどもうそれも無くなる。僕はこれから修羅の道を行く。」
すい…とセオドールが左手を上げた。淡い光が輝く。テレポの術だと、とっさに感じた。
「ま、待ってくれ私は! 私は君の側に…!」
「約束なら忘れていいよ。僕も忘れて…ううん。忘れないで、眠るから。だから」
輝きが増す。私は彼に向けて、走り、手を伸ばす。
「ありがとうルーベル。…元気でな。」
その手が彼に触れる前に、私の意識は遠く弾け飛んだ。
魔物の気配がする。
地を這った私を餌にするつもりなのだろう。だが、今の私はかつてと違い、その気配だけで失った意識を取り戻せる程研ぎすまされている。地に伏せたまま、僅かに右手に力を込めた。
大地から炎が舞い上がる。取り囲んでいた魔物が悲鳴を上げ燃え盛る。そうでないものは離散した。
気配が無くなった後、私は身を起こした。
試練の山…その、麓だった。見上げれば一本の大木がある。
セオドールに命を救われた、その場所―――。
「…セオドール……!」
行かねばならない。彼の元へ。私は誓ったのだ、どんな事があろうと彼の側にいると。
走った。彼と共に時を過ごした、あの山小屋へ。
そこにあったのは、燃え尽きた後の灰の山だった。
一つも痕跡など残さないと言わんばかりに、跡形もなく。
森に被害はなかった。完璧なまでにコントロールされた炎は、間違いなくセオドールのものだった。
呆然とした。何も考える事が出来ないまま、私は家屋があったその場所を、記憶を頼りに歩いた。
入口をつくろうと整備した、簡素な門。魔術の訓練の為に結界を敷いた庭。他愛も無い話しを交わした、長椅子代わりの大木。玄関を入る。立て付けが悪く、まともに閉まらなかった扉を修理した。生活感がまるでなく、埃だらけだった居間も掃除した。折れるのではないかという大黒柱は、数ヶ月がかりで必死になり取り替えた。無事に終えた時は、見事だ、と二人手を叩き合って喜んだではないか――。
「―――どうして。」
膝が崩れた。
「どうしてなんだ…セオドール…!」
違う。愚かだったのは私だ。何一つ彼の苦しみを理解してやれなかった私が、愚かだったのだ。
両手を地につく。涙が出た。悔しくて悔しくて、止まらなかった。灰の山の中、屑折れるように頭を伏せる。このまま、死んでしまいたかった。
こつり。
何かが手に当たった。
暫しの間の後ようやくそれを認識して、私は灰の中をまさぐった。
そこにあったのは、あの魔導書だった。
一つの焦げ跡すらもなく、まるで無傷だった。
それはこの本の持つ魔力なのか、それとも彼がこの本を…家族の思い出を消し去ることを拒んだのか。
泣いた。
かき抱き、ただ泣いた。
圧倒的な喪失感に、泣いて、哭いて吠えるより私には、成す術がなかった。
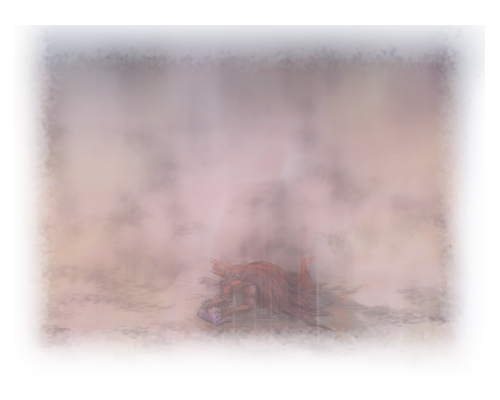
た、ただの不安定な人になってるじゃねーーーか兄さん!!!
まあ、あの多面性の説明にはなるっちゃあなるか…?
やっぱり綺麗に収まりつけてる人は凄いと思いますた。